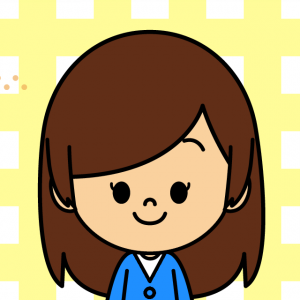平賀源内稀代の発明家は最期何した人だったのか?

平賀源内
- 関係する事件
江戸時代に入り大坂冬の陣・夏の陣も終わって幕府が安定すると、経済や学問・文化が発展するようになりました。武士以外も力を持つようになります。
儒学や蘭学、俳句や浮世絵など様々なものが発達した中、平賀源内は多数のペンネームと使い分け、多彩に活躍した人物です。今回は、蘭学や本草学者から発明家、そして浄瑠璃作者など多彩な才能を発揮した平賀源内の生涯について紹介します。
平賀源内の名前について
源内は通称です。高松藩に再登用された翌年に綴りを元内に変えたと記録が残っています。これは国守(藩主)の姓「源」の字を避けるための措置であり、辞職後は再び「源内」を称しました。
諱は国倫(くにとも)です。1934年製作の「平賀源内略系図」に国棟(くにむね)という別名もありますが、同じ原資料に取材した1986年製作の略系図にはありません。
また、字(あざな)は士彝(しい)です。ただし『戯作者考補遺』(1845年成立)掲載の「処士鳩渓墓碑銘」では「子彝」という字を使っています。
同碑銘は1930年建立の平賀源内墓地修築之碑の裏面に彫られましたが、字は「士彝」に書き換えられました。
源内は数多くの号を使い分けたことでも知られています。
雅号の鳩渓(きゅうけい)は志度村にあった地名「ハトダニ」から取ったとも言われていますし、戯作者としては風来山人(ふうらいさんじん)、悟道軒、天竺浪人(てんじくろうにん)の筆名を用いています。
なお、一字違いの天竺老人は門人の桂川中良の筆名です。浄瑠璃作者としては福内鬼外(ふくうちきがい・ふくちきがい)、俳号は李山(りざん)と名乗りました。
源内の著作の中には、自身をモデルとした「貧家銭内(ひんかぜにない)」という登場人物が出てくる作品もあります。
こうして、源内は本当に多数の名前を使い分けていました。
誕生から跡を継ぐまで
源内は、讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市志度)の白石家の三男として生まれました。父は白石茂左衛門(良房)、母は山下氏です。
兄弟が多数おり、白石家は讃岐高松藩の蔵番という足軽相当(もしくはそれ以下)の身分の家だとされ、源内自身は信濃国佐久郡の信濃源氏大井氏流平賀氏の末裔と称しましたが、『甲陽軍鑑』によれば戦国時代の天文5年(1536)11月に平賀玄信の代に甲斐の武田信虎による侵攻を受け、佐久郡海ノ口城において滅ぼされたとされています。
後に平賀氏は奥州の白石に移り伊達氏に仕え白石姓に改め、さらに伊予宇和島藩に従い四国へ下り、讃岐で帰農したという伝承がありますが詳細ははっきりしません。源内の代で姓を白石から平賀に復姓したと伝わります。
幼少の頃には掛け軸に細工をして「お神酒天神」を作成したとされ、その評判が元で13歳から藩医の元で本草学を学び、儒学も学びます。
また、俳諧グループに属して俳諧なども行いました。寛延2年(1749)に父の死により後役として藩の蔵番となります。
長崎へ遊学
宝暦2年(1752)頃に1年間長崎へ遊学します。源内は低い身分であり、蔵番という仕事があるにもかかわらず、なぜ1年も長崎遊学ができたのかについては謎とさています。
本草学・物産学を好む高松藩主松平頼恭の「内命」があったとする説や、高松の医師で本草愛好家の久保桑閑がパトロンだったなどの説がありますが、詳細は不明です。
源内は家督相続前後に藩の薬園に御薬坊主の下役として登用されたとの説もあり、これは藩主頼恭の意向との話も考えられます。
源内が長崎で何をしていたのかについては史料が不足しているため不明ですが、本草学とオランダ語、医学、油絵などを学んだと推測されています。
留学を終えて長崎から帰った後、宝暦4年(1754)7月に「近年病身」を理由にして藩に蔵番退役願を提出し、妹に婿養子を迎えさせて家督を妹婿に譲っています。
宝暦5年(1755)には量程器(歩いた距離を測る器具)や磁針器(方角を測る器具。オランダ人製作の同器具を模倣したもの)を製作しています。
大坂、京都でも学び、さらに宝暦6年(1756)には江戸に下って本草学者田村元雄(藍水)に弟子入りして本草学を学び、漢学を習得するために林家にも入門、聖堂に寄宿しています。林家の塾に学んだのは儒学(漢学)を学ぶことを本旨としたのではなく、漢文で書かれた本草学に関連する古典を読解するためでした。
源内の「漢文力」はさほど無かったとする見解もあり、「学術は無き人也」(江戸中期の儒学者柴野栗山)との源内評も存在しています。2回目の長崎遊学では鉱山の採掘や精錬の技術を学びました。
高松藩に召し抱えられるも自由に活動
宝暦7年(1757)、日本最初の薬品会(薬種・物産を展示する会)を発案し、その後も江戸で何度も物産会を開催、新進の本草学者として名が知られるようになります。
しかし、宝暦9年(1759)に高松藩は医術修行という名目で三人扶持を源内に与え、召し抱えてしまったのです。源内はこれを仕官とは考えていなかったようですが、藩は源内を家臣として扱っています。宝暦11年(1761)に江戸に戻るため再び辞職。
このとき「仕官お構い」(奉公構)となり、以後幕臣への登用を含め他家への仕官が不可能となってしまいました。一説には源内は大藩か幕府に仕官したいとの野心を抱いていたとも言われていますが、それも不可能となったのでした。
宝暦11年(1761)には伊豆で鉱床を発見し、産物のブローカーなども行います。
物産博覧会をたびたび開催し、この頃には幕府老中の田沼意次にも知られるようになっています。宝暦12年(1762)には物産会として第5回となる「東都薬品会」を江戸の湯島にて開催。江戸において知名度も上がり、杉田玄白や中川淳庵らと交友するようになりました。宝暦13年(1763)には『物類品隲ぶつるいひんしつ』を刊行し、オランダ博物学に関心をもち、洋書の入手に専念しますが、源内には語学の知識がなく、オランダ通詞に読み分けさせて読解に務めました。文芸活動も行い、談義本の類を執筆しています。
明和年間には産業起業的な活動も行っていました。明和3年(1766)から武蔵川越藩の秋元凉朝の依頼で奥秩父の川越藩秩父大滝(現在の秩父市大滝)の中津川で鉱山開発を行い、石綿などを発見しています(現在のニッチツ秩父鉱山)。
秩父における炭焼、荒川通船工事の指導などにも携わり、現在でも奥秩父の中津峡付近には、源内が設計し長く逗留した建物が「源内居」として残っています。
安永2年(1773)には出羽秋田藩主の佐竹義敦に招かれて鉱山開発の指導を行うため阿仁鉱山を訪れ、その途中に立ち寄った角館で、秋田藩士小田野直武に蘭画の技法を伝えるとともに、角館の次に立ち寄った上桧木内(秋田県仙北市西木町)で、子どもたちに熱気球の原理を応用した遊びを教えたと言われており、これが伝統行事上桧木内の紙風船上げの起源と言われています。
後半生と最期
安永5年(1776年)には長崎で手に入れたエレキテル(静電気発生機)を修理して復元。話題となったエレキテルを高級見せ物にすることによって謝礼を貰い生活費にし、余興まで加えて見物客の誘致に努めました。
鉱山開発の指導や戯作・浄瑠璃まで書き散らした文芸活動も生活費を稼ぐためだったのです。しかし、結果的に秩父鉱山は挫折し、「憤激と自棄」(門人の狂歌師平秩東作の評)のつのる中で多くの戯文を弄すなど生活は荒れていきました。経済状況も悪化し、安永7年(1778)には「功ならず名斗(ばかり)遂(とげ)て年暮ぬ」という一句を詠んでいます。
安永8年(1779)夏には橋本町の邸へ移ります。11月20日夜、神田の源内宅に門人の久五郎と友人の丈右衛門が止宿していたところ、明け方に彼らは「口論」を起こして源内は抜刀。両人に手傷を負わせ、久五郎は傷がもとで死去。
源内はこの事件が起こる前から、よく癇癪を起こしていたとされています(源内による殺傷事件の内容については諸説あり)。
翌21日に投獄され、12月18日に破傷風によって獄死しました。享年52。
獄死した遺体を引き取ったのは平秩東作とされています。杉田玄白らの手により葬儀が行われましたが、幕府の許可が下りず、墓碑もなく遺体もないままの葬儀となったそうです。
ただし、源内の晩年については諸説あります。
大名屋敷の修理を請け負った際、酔っていたために修理計画書を盗まれたと勘違いして大工の秋田屋九五郎ら棟梁2人を殺傷したとも、後年に逃げ延びて書類としては死亡したままで田沼意次ないしは故郷高松藩(旧主である高松松平家)の庇護下に置かれて天寿を全うしたとも伝えられていますが、いずれも詳細は不明とされています。
大正13年(1924年)、従五位を追贈されました。
源内の人物評と業績
- 人物評
- 源内は、天才、または異才と評されました。幕府が鎖国を行っていた当時の日本で、蘭学者として油絵や鉱山開発など外国の文化・技術を紹介しただけでなく、文学者としても戯作の開祖とされており、人形浄瑠璃などに多くの作品を残しました。また源内焼などの焼き物を作成したりするなど、多彩な分野で活躍しています。
男色家であったとされ、生涯にわたって妻帯せず、歌舞伎役者らを贔屓にして愛したと言われています。特に、二代目瀬川菊之丞(瀬川路考)との仲は有名で、晩年の殺傷事件も男色に関するものが起因していたとも言われています。
『解体新書』を翻訳した杉田玄白をはじめ、当時の蘭学者の間では源内の名は広く知られており、玄白の回想録である『蘭学事始』は、源内との対話に一章を割いています。源内の墓碑銘を記したのも玄白です。 - 業績
- 発明家としての業績には、オランダ製の静電気発生装置エレキテルの紹介、火浣布の開発があります。気球や電気の研究なども実用化寸前までこぎ着けていたといわれます。
ただし、結局これらは実用的研究には一切結びついておらず、後世の評価を二分する一因となりました。
エレキテルの修復にあっては、その原理について源内自身はよく知らなかったにもかかわらず、修復に成功したと伝わります。
1765年に温度計「日本創製寒熱昇降器」を製作。現存していませんが、源内の参照したオランダの書物及びその原典のフランスの書物の記述からアルコール温度計だったとみられています。この温度計には、極寒、寒、冷、平、暖、暑、極暑の文字列のほか数字列も記されており、現在の華氏を採用していました。 - 土用のウナギ
- 土用の丑の日にウナギを食べる風習は、源内が発祥との説は有名です。
この通説は土用の丑の日の由来としても平賀源内の業績としても最も知られたもののひとつですが、両者を結び付ける明確な根拠となる一次資料や著作は存在していません。
また明和6年(1769)には歯磨き粉『漱石膏』の作詞作曲を手がけ、安永4年(1775)には音羽屋多吉の清水餅の広告コピーを手がけてそれぞれ報酬を受けており、これらをもって日本におけるコピーライターのはしりとも評されることがあります。
浄瑠璃作者としては福内鬼外の筆名で執筆。時代物を多く手がけ、作品の多くは五段形式や多段形式で、世話物の要素が加わっていると評価されています。
狂歌で知られる大田南畝の狂詩狂文集『寝惚先生文集』に序文を寄せています。強精薬の材料にする淫水調達のため若侍100人と御殿女中100人がいっせいに交わる話『長枕褥合戦』(ながまくら しとねかっせん)のような奇抜な好色本も書いており、幅広い作品が残っています。衆道関連の著作として、水虎山人名義で 1764年(明和元年)に『菊の園』、安永4年(1775年)に陰間茶屋案内書の『男色細見』を著わしました。
鈴木春信と共に絵暦交換会を催し、浮世絵の隆盛に一役買った他、博覧会の開催を提案、江戸湯島で日本初の博覧会「東都薬品会」が開催されています。
文章の「起承転結」を説明する際によく使われる「京都三条糸屋の娘 姉は十八妹は十五 諸国大名弓矢で殺す 糸屋の娘は目で殺す 」の作者との説もあります。
金唐革がブームとなり、それによる日本の金銀銅の流失を懸念して、和紙の模造品である金唐革紙(擬革紙)を発明しました。
- 関係する事件

- 執筆者 葉月 智世(ライター) 学生時代から歴史や地理が好きで、史跡や寺社仏閣巡りを楽しみ、古文書などを調べてきました。特に日本史ででは中世、世界史ではヨーロッパ史に強く、一次資料などの資料はもちろん、エンタメ歴史小説まで幅広く読んでいます。 好きな武将や城は多すぎてなかなか挙げられませんが、特に松永久秀・明智光秀、城であれば彦根城・伏見城が好き。武将の人生や城の歴史について話し始めると止まらない一面もあります。